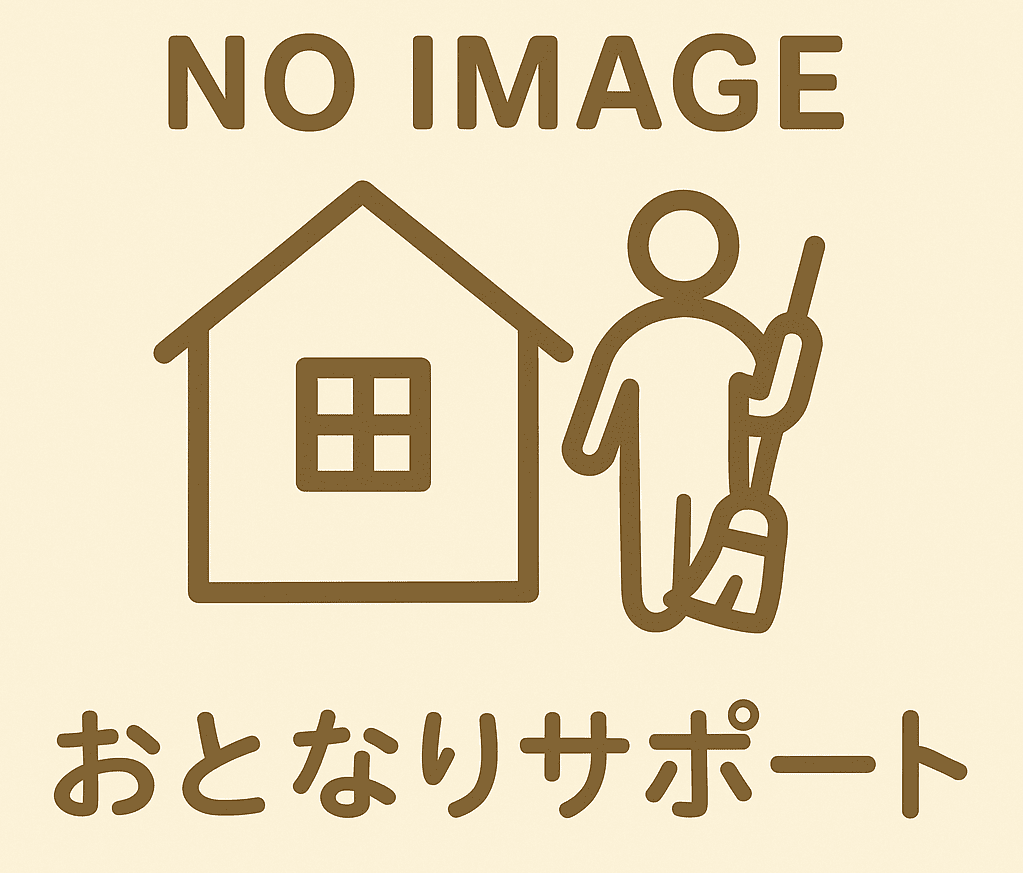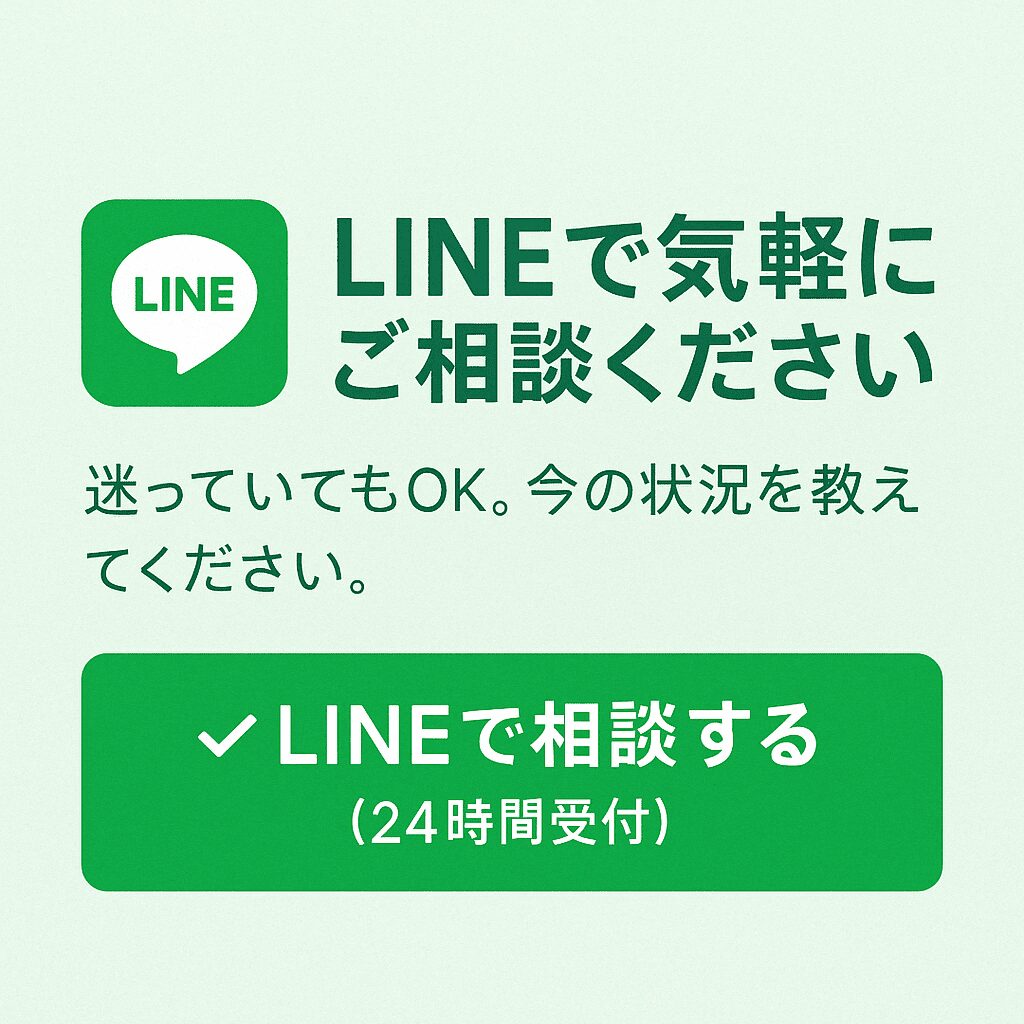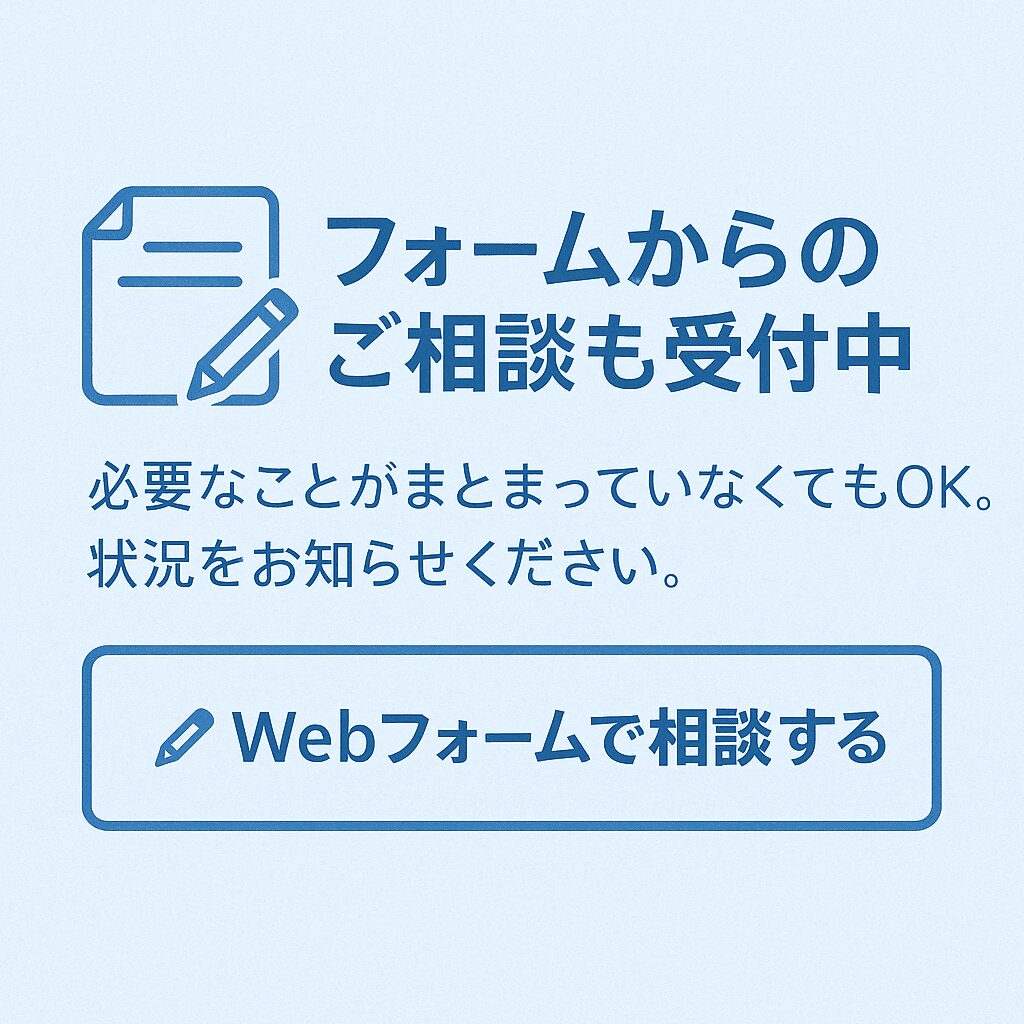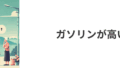災害時も安心して暮らすための高齢者の備え方
年々、自然災害のニュースを目にする機会が増えていますね。地震、大雨、台風など、どれもいつどこで起きるか分からない時代です。特に一人暮らしをされている高齢の方にとっては、万が一のときにすぐに助けを呼ぶのが難しいこともあります。
南島原市では、2020年の統計で高齢化率が36.2%となっており、全国平均の28.1%を大きく上回っています。だからこそ、日頃からの備えがとても大切になってきます。
この記事では、南島原市で暮らす一人暮らしの高齢者の方に向けて、災害時の備え方をわかりやすくお伝えしますね。
地域特有の災害リスクを知っておく
南島原市は、雲仙普賢岳のある島原半島に位置しており、「雲仙断層帯南西部」と呼ばれる活断層の影響もある地域です。過去には土砂災害や地震の被害も起きていて、これからの将来に向けても油断はできません。
こうした地域特有のリスクをきちんと把握しておくことで、いざというときの行動も落ち着いて取れるようになります。
市役所では「避難行動要支援者名簿」の登録制度もあります。自分で避難するのが難しいと感じている方や、ご家族が遠方に住んでいる場合は、早めに登録しておくと、災害時に行政やご近所の方の支援を受けやすくなります。
家の中の安全対策を進めておく
お部屋の中をちょっと見直すだけでも、災害時のケガや被害をぐんと減らせます。
たとえば、タンスや冷蔵庫などの大型家具は、地震で倒れてこないように壁に固定しておくと安心です。
また、懐中電灯や電池、非常用ラジオ、笛なども、決まった場所にまとめておくと、暗い中でもすぐに使えますよ。停電してもトイレに行けるように、センサーライトを設置しておくのもおすすめです。
浴室やキッチンの収納棚も、重たいものはなるべく下の方へ移しておくと安全です。
備蓄の工夫は「ローリングストック法」で
非常食や飲料水、常備薬などは、2〜3日分は備えておきたいところですが、どこに置いたか忘れたり、気づけば賞味期限が切れていた…なんてこともありますよね。
そんなときは「ローリングストック法」という方法が便利です。これは、普段から少し多めに食材や日用品を買っておいて、使った分だけ補充していく方法です。特別な準備をしなくても、日常の延長で備蓄できるのでおすすめです。
また、お薬を飲まれている方は、処方箋の写しやお薬手帳をまとめておくと、万一病院に行けないときにも役立ちますよ。
福祉避難所の存在を知っておこう
市内には、通常の避難所とは別に「福祉避難所」が用意されている場合があります。これは、要介護の方や持病のある方など、一般の避難所では過ごしづらい人のための場所です。
ただし、福祉避難所は災害発生後すぐには開設されず、状況を見て必要と判断された場合に開設されます。そのため「自分は対象になるのか」「利用にはどういう準備がいるのか」など、市役所に確認しておくと安心です。
また、通院や介護が必要な方は、かかりつけの医療機関やケアマネジャーと災害時の対応について日頃から話し合っておくことも大切です。
遠くに住むご家族とも連携を
南島原市にお住まいで、身内が遠方にいらっしゃる方も多いと思います。災害時にはすぐに連絡が取れなくなることもありますので「災害があったらLINEで連絡」「電話が通じなければ〇〇さんに連絡」など、事前に決めておくことが大切です。
LINEやメールが不慣れな方も、事前に設定しておけば簡単に連絡が取れるようになります。ご家族の方が遠くにいる場合でも、私たち便利屋が間に入って見守りや安否確認をすることもできますよ。
まとめ
- 南島原市は高齢化率が36.2%と高く、災害に備えた暮らしがますます大切です。
- 雲仙断層帯による地震リスクや土砂災害にも注意が必要です
- 避難行動要支援者名簿の登録で災害時の支援が受けやすくなります
- 備蓄は「ローリングストック法」で無理なく続けましょう
- 福祉避難所の情報やご家族との連絡方法も、日頃から確認しておくことが安心につながります