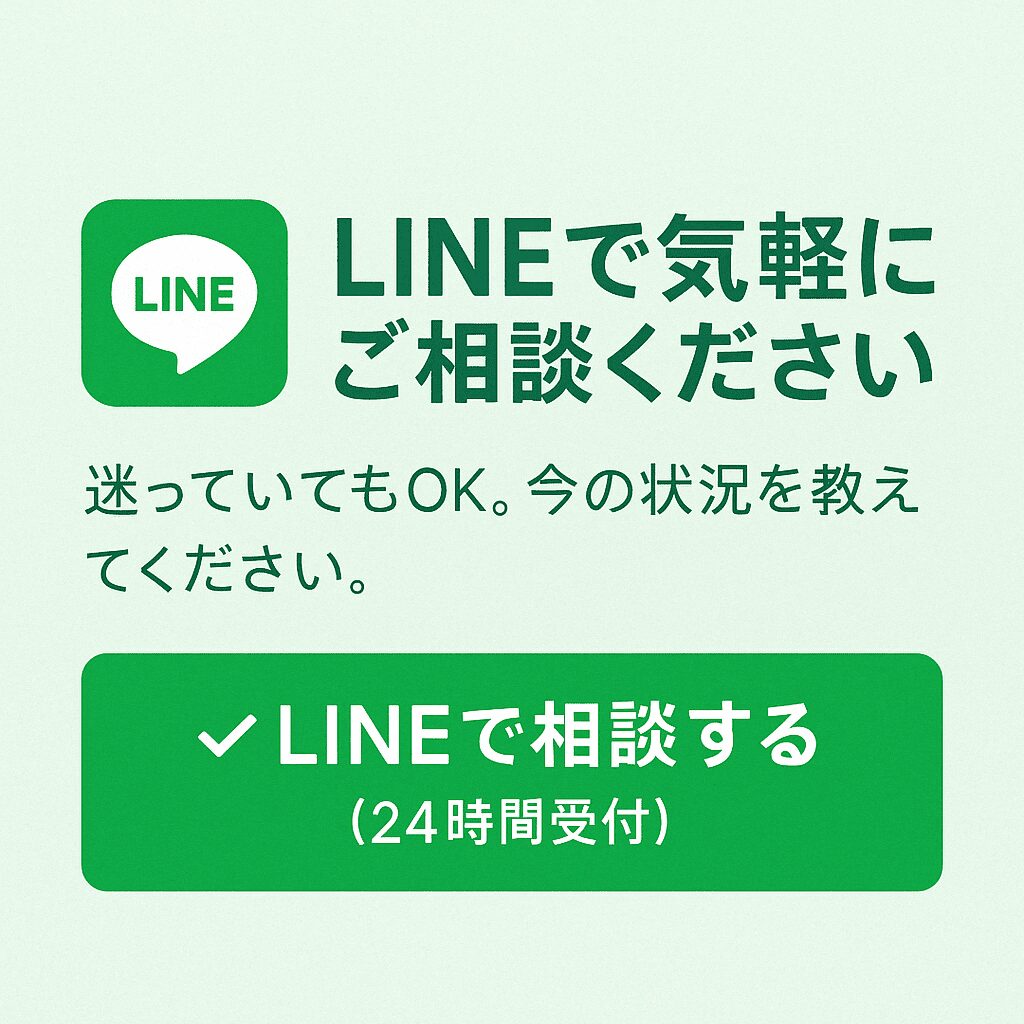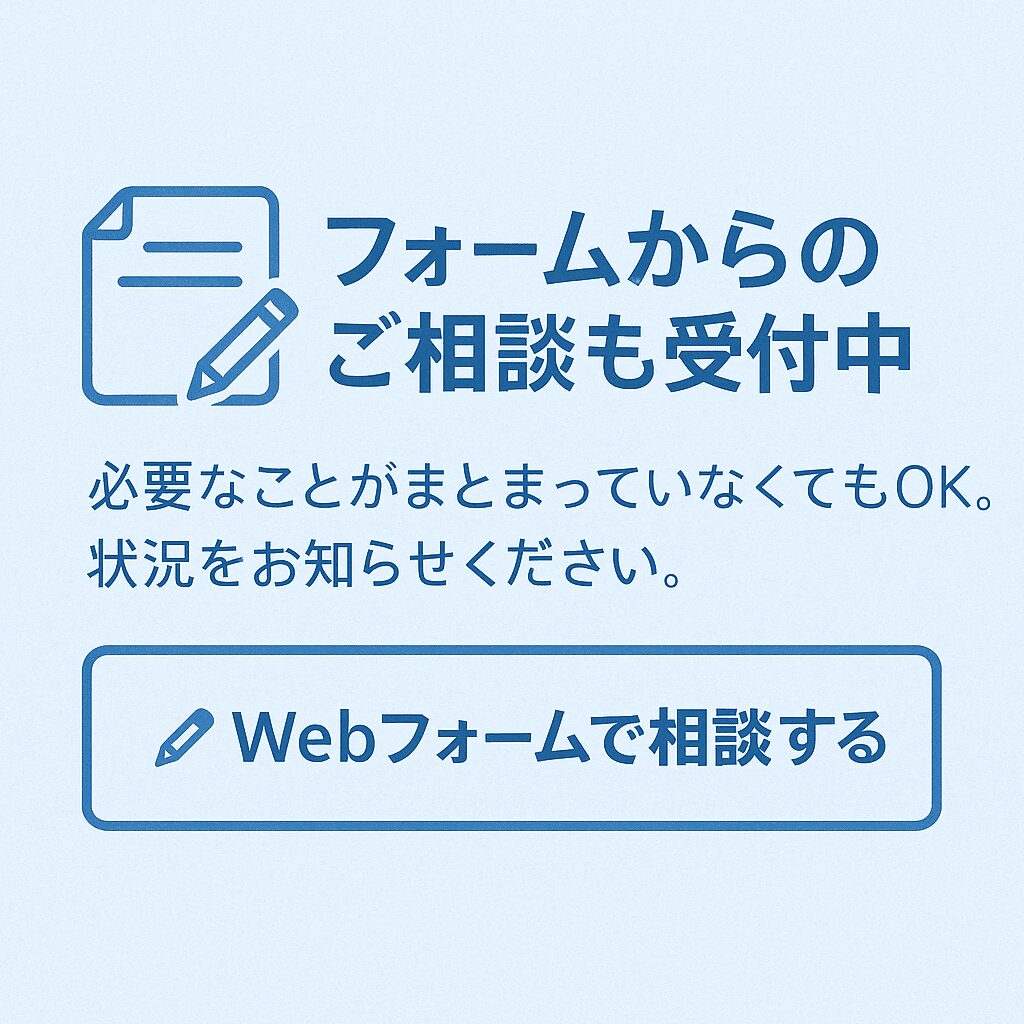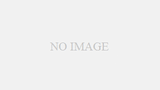留守がちな親に手紙で「安否確認」する方法
「電話をかけてもなかなか出ない」「LINEも既読がつかない」——そんなとき、心配になりますよね。
私も、母が何日も留守で連絡が取れなかったとき、とても不安になったことがあります。でも、そんなときに試してみたのが「手紙での安否確認」でした。
今回は、スマホや電話が苦手な高齢の方にも届きやすい、“手紙”を使った安心の伝え方をご紹介します。
手紙のいいところは「タイミングを選ばない」
電話は出られないときもありますが、手紙ならポストに入れておけば、本人の都合のよいときにゆっくり読めます。
私は、「元気にしてる?最近寒くなってきたね」と気づかいを込めた内容で送りました。母も「うれしかったよ、あれ見てすぐ電話したの」と言ってくれて。
定期的に「ひとこと便り」を送る
季節の変わり目や、月に一度など、決まったタイミングで送ることで、「○○さんからの手紙が来るはず」と本人も楽しみにしてくれるようになります。
私の知人は、月に1回「写真付きハガキ」を送っていて、それを冷蔵庫に貼って見守り代わりにしているそうです。
手紙の最後に「簡単な返信」を促す一文を
「お元気なら“○”をつけて、このハガキをポストに入れてね」など、返事がしやすいように促すと、やりとりがスムーズになります。
返信用のハガキや切手を同封しておくのもおすすめです。「返事をもらうこと」が目的ではなく、「無事を確認する」きっかけづくりなんですね。
手紙+αの連絡方法と組み合わせて
留守がちなお宅には、手紙と一緒に「玄関の呼び鈴チャイムを鳴らす」など、家の近くに住む知人と協力する方法もあります。
私は近所の親戚に「この週に手紙を出す予定だから、ついでに様子見てくれたら助かる」とお願いしています。
書き方のポイントは「やさしいトーンで」
「どうして電話に出ないの!」と責めるような言葉よりも、「ちょっと気になったから手紙を書いたよ」「体に気をつけてね」と、穏やかな文章にするのがポイントです。
心がけたいのは、「心配させる」より「安心させる」手紙なんですね。
おわりに
手紙は、アナログだけれど、とてもあたたかくて、ゆっくり届く気持ちの橋渡しです。
デジタルに頼れないときこそ、やさしく届く手紙の力を活かして、親御さんとのつながりを守っていきたいですね。