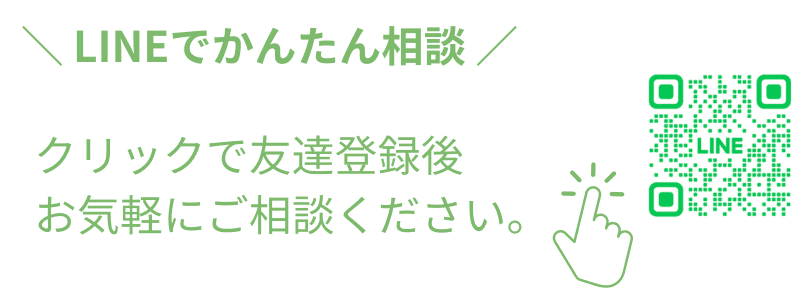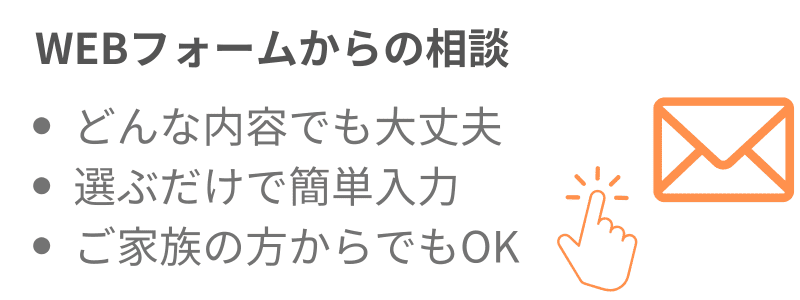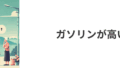増える高齢者の「買い物難民」
「最近、買い物に行くのがしんどくなってきた」「近くのお店が閉まってしまって、遠くまで行かないと…」そんな声を、南島原でもよく聞くようになりました。
高齢者が食料や日用品を手に入れられなくなる状況は、「買い物難民」と呼ばれ、全国的にも深刻な社会問題となっています。
今回は、この「買い物難民」の実態や原因、南島原で今できる支援の方法について、全国の事例も交えてわかりやすくご紹介します。
「買い物難民」とは?どんな人が当てはまるの?
「買い物難民」とは、主に高齢者の中で、日常的な買い物が困難になっている方を指す言葉です。
国の調査では、65歳以上の高齢者のうち、なんと約25%(4人に1人)が「買い物が不便」と感じていることがわかっています。特に、地方や過疎地域ではこの傾向が強く、商店の閉鎖や交通手段の減少が主な原因です。
南島原市のように、高齢化率が40%を超える地域では、今後さらにこの問題が広がることが予想されています。
なぜ買い物が困難になる?
買い物ができなくなる背景には、いくつかの理由があります。ひとつは移動手段の問題です。年齢を重ねて車の運転が難しくなると、バスやタクシーが頼りになりますが、南島原では本数が少なく、時間も限られているため、自由に動けるとは言えません。
また、体力の低下や関節の痛みで長時間歩けない、重い荷物を持てないなどの身体的な不安も影響しています。誰かに頼るのも気が引けて、結果的に「あるもので済ませる」ようになり、栄養不足や孤立感につながってしまうこともあるんです。
南島原市の現状と課題
南島原でも、昔は歩いて行けた近所の商店が閉まってしまった地域が少なくありません。スーパーやドラッグストアは特定の地域に集中していて、車がないと不便な立地が多いです。
加えて、単身世帯や高齢者夫婦だけの家庭が増えており、買い物に行くのが難しくなっても助けを頼める人がいないという声もよく聞かれます。
他地域での取り組みから学べること
全国では、この問題に対してさまざまな取り組みが始まっています。たとえば、長野県では移動販売車が定期的に地域を巡回し、生鮮食品や日用品を販売するサービスが高齢者に喜ばれています。
また、岡山県の一部地域では、地域住民が支え合う「お買い物サポート隊」が立ち上がり、週に数回、希望者の家を回って買い物を代行する仕組みが運用されています。こういった仕組みは、南島原でも今後取り入れていけるヒントになるかもしれませんね。
便利屋だからできる、買い物のサポート
私たち「おとなりサポート」では、南島原市内で高齢者の方の買い物支援を行っています。お客様と一緒にお店へ行く「同行型」、買い物リストをもとに代わりにお店をまわる「代行型」、どちらにも対応可能です。
冷蔵庫の中を一緒に確認しながら「今週は何が足りないか」を話し合ったり、商品の名前が分からなくても「こんな袋で、こういう味だった」という情報から一緒に探すこともできますよ。
買い物は「生きること」に直結しています
食べたいものを食べる、必要な物を揃える。それが自由にできないというのは、本当に不安で、つらいことです。とくに高齢になると、外に出るきっかけが減ることで心の元気も失われてしまいます。
だからこそ、買い物支援は「ただの代行」ではなく「その人らしい暮らしを支える」大切なサポートなんです。無理せず、気軽に頼れる仕組みがあることを、もっと多くの方に知っていただきたいと思っています。
まとめ
- 全国では高齢者の約25%が「買い物に不便を感じている」とされ、南島原市でも同様の課題が広がっている
- 地域のお店の減少、交通手段の不足、身体的な制約が「買い物難民」を生み出す
- 他地域では移動販売車や住民参加型の買い物サポートなどの成功例がある
- 南島原市の便利屋「おとなりサポート」では、買い物代行や同行サポートを提供中
- 買い物支援は、高齢者の暮らしと心の健康を支える大切なサポートです