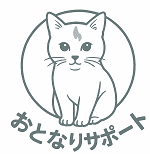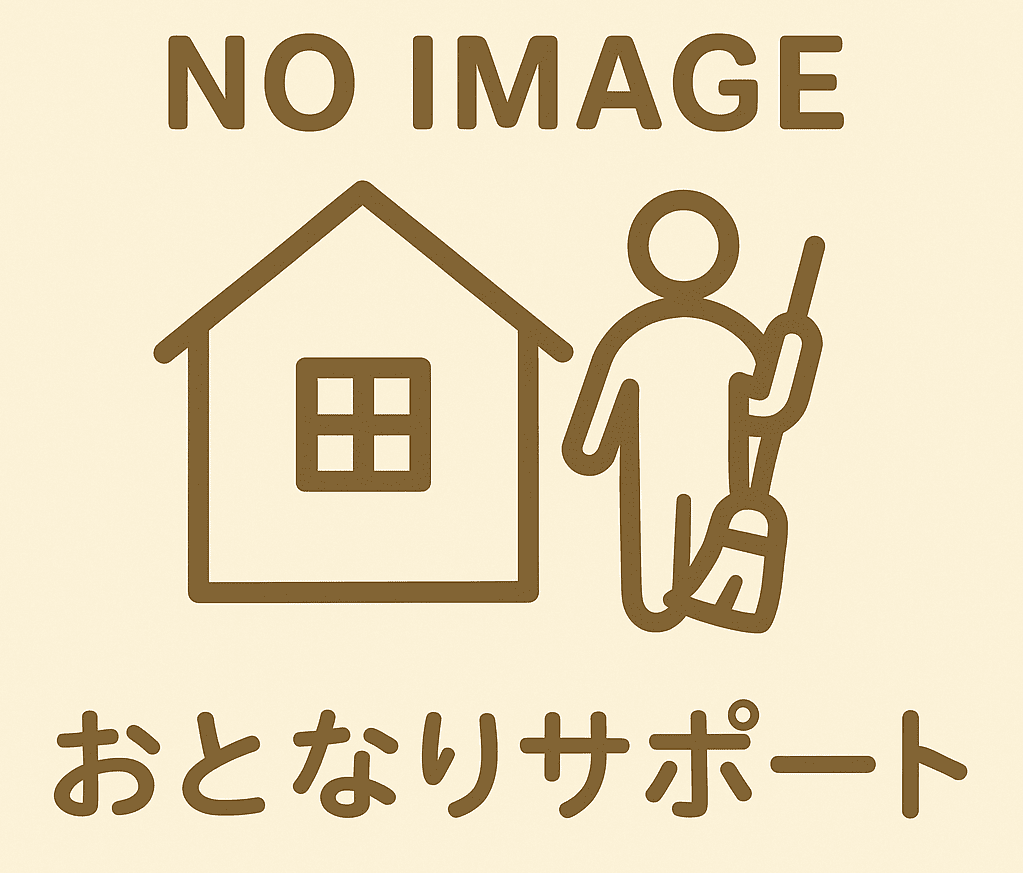一周忌の準備、最低限やるべきことリスト
「気づいたらもう一年、早いわね……」
家族を見送ってから一年。故人を偲ぶ大切な節目が「一周忌」です。しかし、いざ準備となると「一周忌は何をするの?」「お寺と自宅どちらで行う?」「施主は何を用意すべき?」と迷う方も多いです。ここでは、一周忌に必要なもの・やることをわかりやすく整理しました。
日程と場所を決める
- 日程:命日からちょうど1年後、または前倒しで直前の週末に行うのが一般的です。
- 場所:自宅、お寺(菩提寺)、斎場・会館などから選べます。お寺で一周忌を行う場合は、お供えやお布施を用意して伺います。自宅で行う場合は、仏壇まわりや会場を整え、参列者を迎えられる準備が必要です。
一周忌でやること(施主の役割)
施主は一周忌の中心的な役割を担います。以下の流れを押さえておくと安心です。
- 日程・会場・僧侶を決める
- 参列者へ案内(はがき・電話・LINEなど)
- お布施・御供物・御花の準備
- 会食や引き物(返礼品)の手配
- 当日の進行と挨拶
一周忌の持ち物リスト
施主が用意するもの
- お布施(相場:3万〜5万円程度)
- お供え(果物・菓子・線香・ろうそくなど)
- 花(仏花やアレンジメント)
- 引き物(菓子折り・タオル・カタログギフトなど)
参列者が持参するもの
- 香典(表書きは「御仏前」)
- 数珠
- 喪服または地味な服装
- ハンカチや小物入れ
家族のみで行う場合でも、数珠や香典など基本的な持ち物は忘れずに準備しましょう。
一周忌の準備チェックリスト(時系列)
- 1ヶ月前:僧侶・会場・仕出し弁当・引き物を予約
- 2〜3週間前:参列者へ案内
- 1週間前:花・供物・当日の流れを確認
- 前日〜当日:服装・持ち物を確認し、施主の挨拶を準備
お寺で一周忌を行う場合
- 僧侶に読経を依頼し、法要後に焼香
- 仏前に供える花や供物を持参
- 施主はお布施を用意し、法要後に僧侶へお渡しする
- 会食をお寺近くの会場で手配するケースも多い
自宅で一周忌を行う場合
- 仏壇や遺影を整え、祭壇を用意
- 花や供物を飾り、僧侶に来てもらって読経を依頼
- 家族のみで行う場合は、会食を弁当形式にして簡略化することも可能
一周忌の挨拶と当日の流れ
- 僧侶の読経
- 焼香
- 施主の挨拶:「本日はご多用の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。皆さまと共に故人を偲ぶことができ、心より感謝申し上げます。」
- 会食またはお弁当配布
オンライン参加や高齢者対応も考慮を
遠方の家族や高齢の親族が参加しにくい場合は、オンラインでの法要や、当日の録画配信なども検討できます。また、送迎サービスや宿泊先の案内も添えておくと、安心して参加してもらえます。
一周忌にかかる費用の目安
- お布施:3万〜5万円
- 会食:1人3,000〜5,000円
- 引き物:1人1,000〜3,000円
- 花・供物:5,000〜1万円
ご予算に応じて、会食を弁当形式にするなど、調整も可能です。
よくある質問と対応策
- 一周忌はどこでやる? → 自宅・お寺・斎場のいずれでも可能。
- 一周忌に持っていくものは? → 香典・数珠・喪服が基本。
- 一周忌のお供えは? → 果物や菓子、仏花が定番。
- 一周忌の時間帯は? → 午前〜午後早めに行うのが一般的。
法要後のマナーとお礼
参列者へのお礼状や、香典返しの送付も忘れずに。
文例:「このたびは故人の一周忌にご参列いただき、心より感謝申し上げます……」
返礼品の発送時には、メッセージカードや写真を添えても良いですね。
おわりに
一周忌は、形式的な儀式ではなく「家族で気持ちを整える時間」です。場所や規模にこだわる必要はなく、自宅でもお寺でも、ご家族に合った方法で構いません。大切なのは、感謝の気持ちを込めて故人を偲ぶこと。準備をシンプルに整え、無理のない一周忌を迎えましょう。
おとなりサポートにご相談ください
「掃除や会場準備が大変」「お供えや花の手配をどうしよう」——そんなときは南島原の便利屋 おとなりサポート にご相談ください。
- 法要前の片付けや掃除代行
- 仏花や供物の手配サポート
- 高齢のご家族を支える送迎や付き添い
地元ならではの安心感で、一周忌を無理なく迎えるお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。