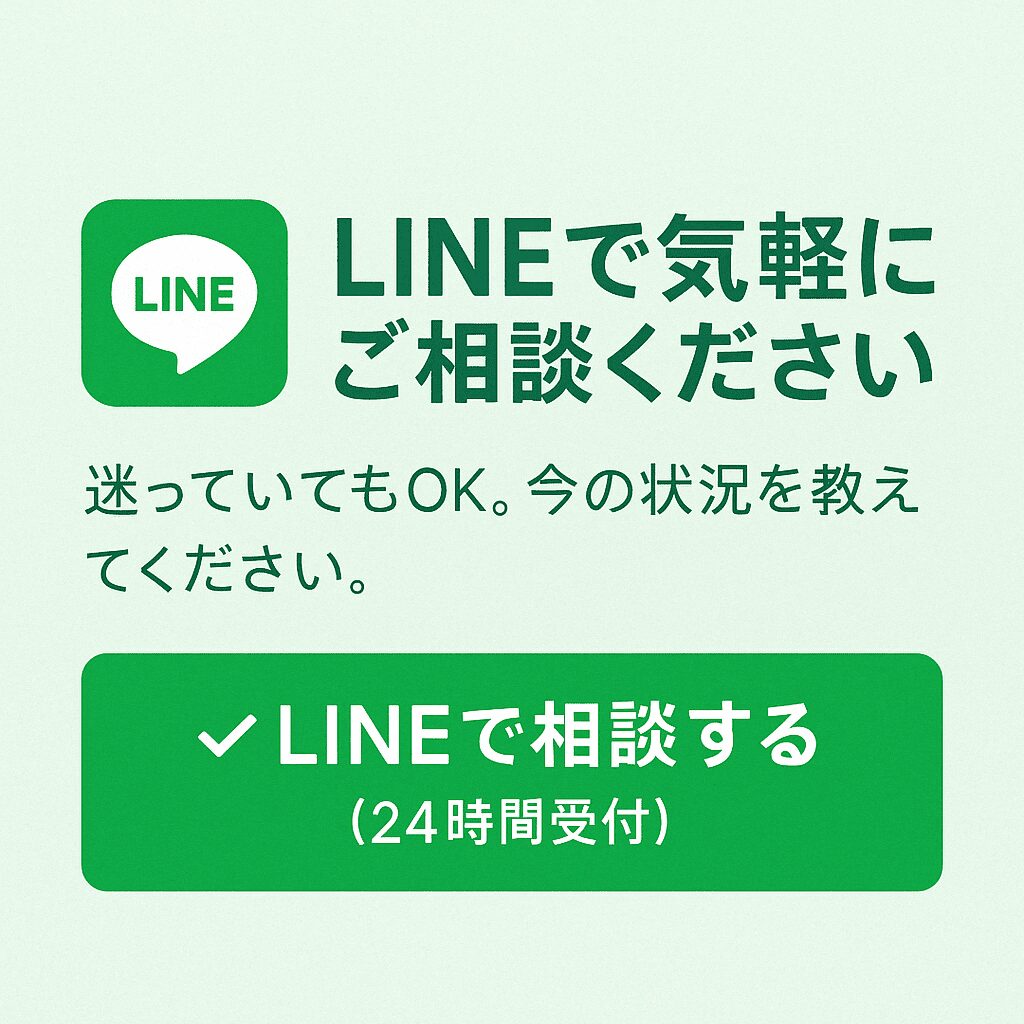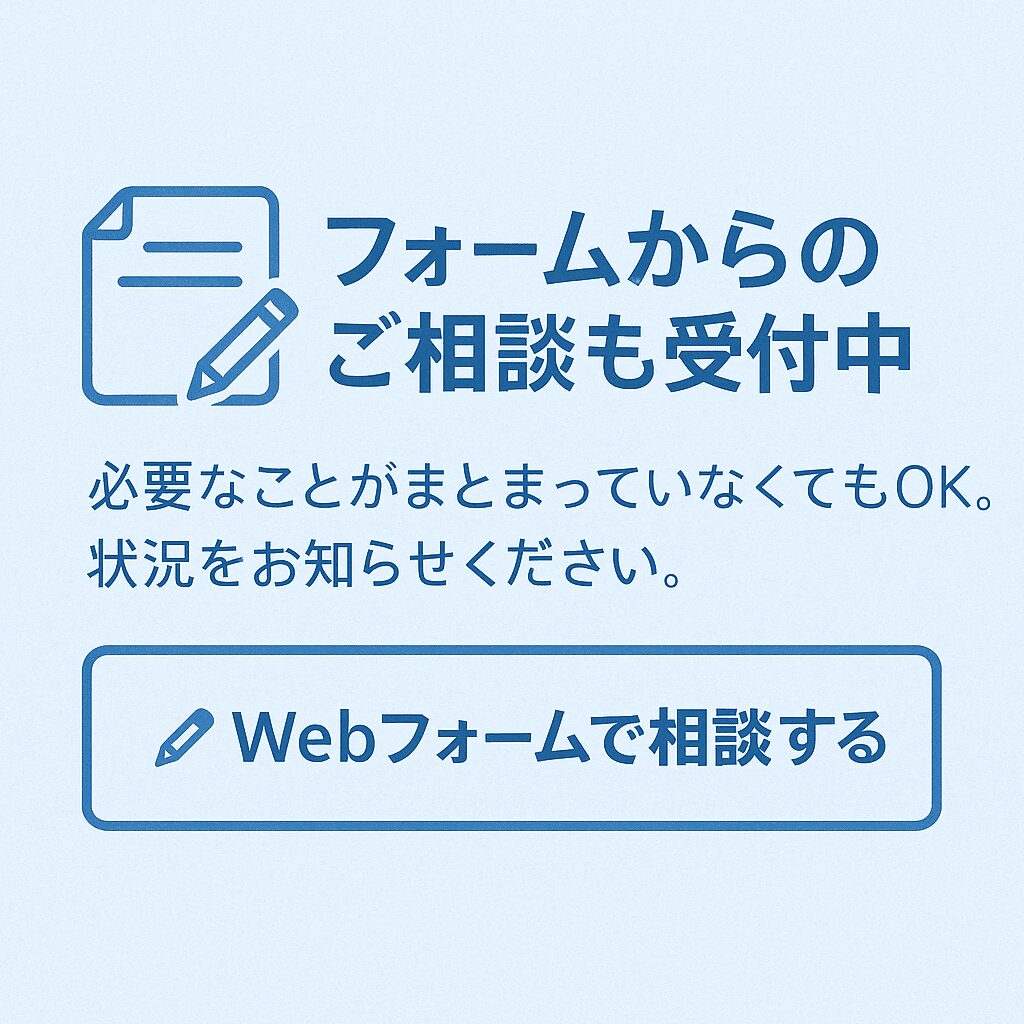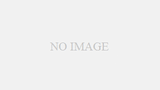模様替えで動線が悪くならない配置のコツ
「家具を動かしたら、なんだか暮らしにくくなった」「通りにくい、よけにくい…」——そんな“模様替えの失敗”、ありませんか?
お部屋の印象を変える模様替え。でも、配置によって暮らしやすさが大きく変わることも忘れてはいけません。
今回は、高齢の方の安全や暮らしやすさにも配慮した、「動線を崩さない模様替えのコツ」をご紹介します。
動線の基本は「最短距離」と「曲がらない」
生活の中でよく通るルート(リビング〜キッチン、寝室〜トイレなど)は、できるだけ直線で、よける物が少ないほうが◎です。
私は、母の寝室〜トイレの間にあった棚を移動し、夜中でもまっすぐ歩けるようにしたら、つまずきが減って安心できました。
家具は「壁沿い」+「高さをそろえる」と圧迫感減
大きな家具を通り道の途中に置くと、狭く感じて動線が悪くなります。
私は、背の高い棚は壁際に、低めの家具は手前に配置するようにしています。視線が抜けて、広く見える効果もあります。
「イスを引く・ドアを開ける」動作も想定して配置
通路幅はあるように見えても、イスを引いたりドアを開けたりすると実際は通りにくいことも。
私は、テーブルと壁の間は最低70cm、ドア前は90cm以上あけるようにしています。高齢の親には特に大切な配慮です。
コードやカーペットの「つまずき」を減らす
模様替えでテレビや照明の位置が変わると、配線コードが通路を横切ることも。
私は、床に這わせるコードにはカバーをつけ、ラグの端には滑り止めシートを敷くようにしています。転倒リスクを減らす工夫です。
家具の配置は「1週間だけ仮おき」して試す
模様替えは、やってみないと分からないことも多いもの。
私は「まず仮おきしてみて、1週間暮らして不便がないか確かめる」ことを習慣にしています。違和感があればすぐに戻せばOK。
おわりに
模様替えは“見た目”だけでなく“動きやすさ”が大切。
暮らしの中での「通りやすさ」「安全性」を意識して配置を考えれば、気持ちも空間もスッキリしますよ。
無理なく、少しずつ変えてみてくださいね。