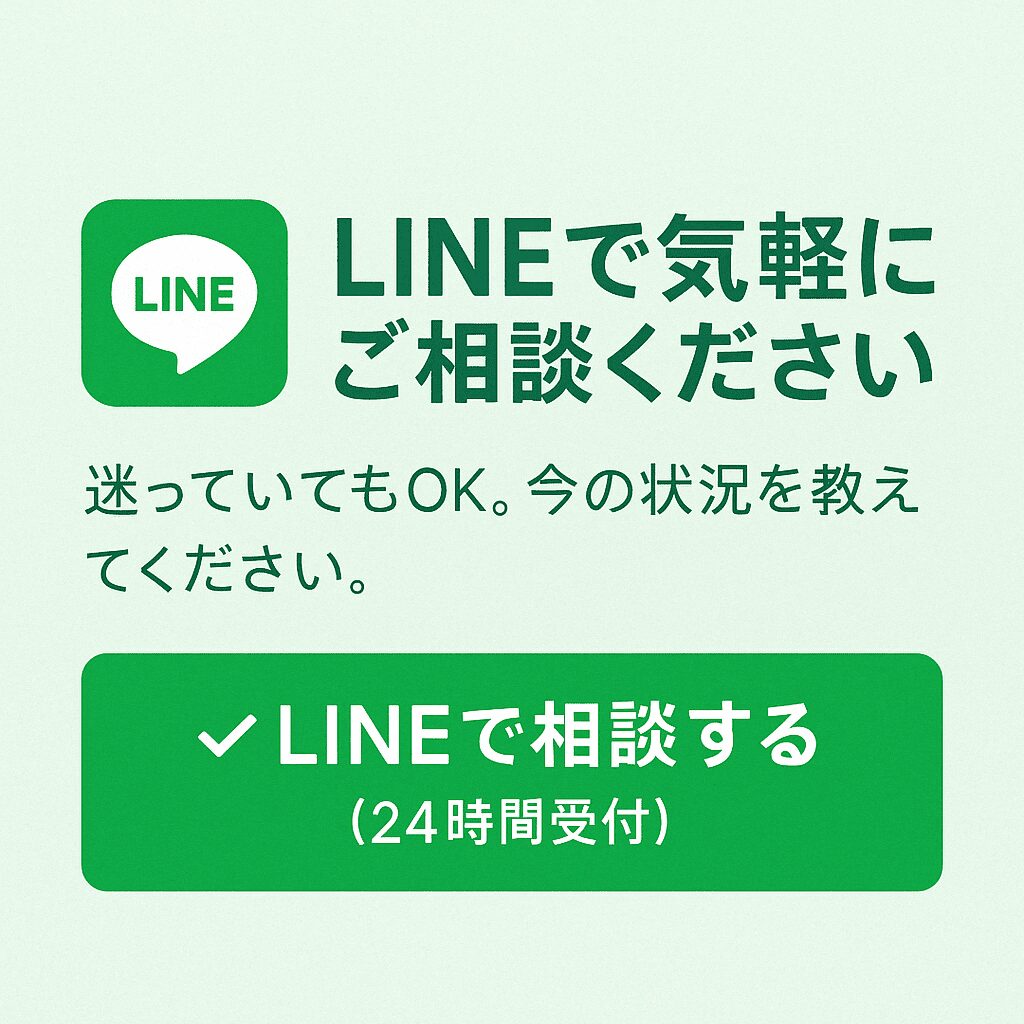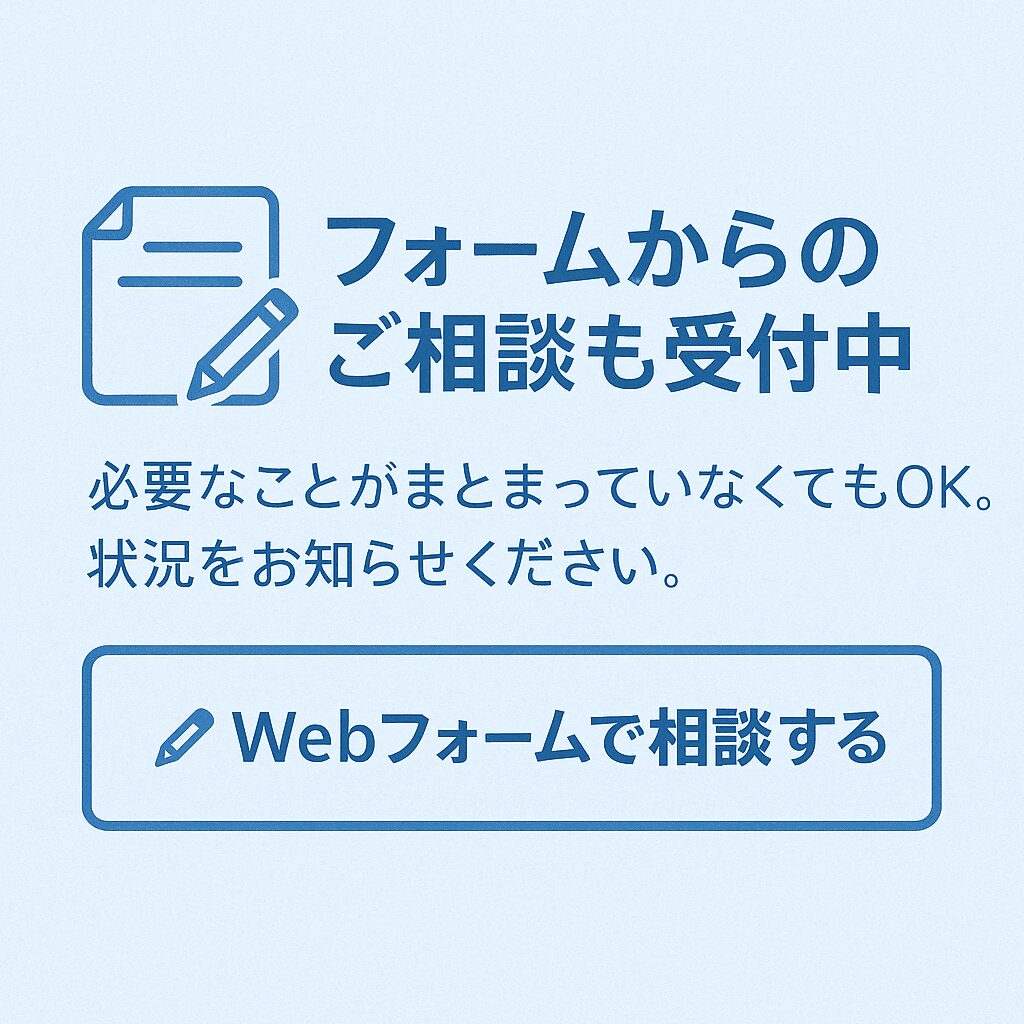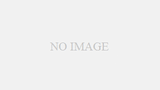無理しない見守り、自分でできる範囲を知ることが第一歩
「何かあったらすぐ駆けつけたいけど、毎日は難しい」「親が嫌がらない程度に、見守りたい」——そんな思い、ありませんか?
私自身も、母を見守る中で「どこまで手を出して、どこまで任せていいのか」に迷うことがよくありました。
今回は、“無理をしない見守り”の考え方と、自分でできる範囲を知るためのヒントをお届けします。
「何でもしてあげる」は、本人の自立を妨げることも
親が年齢を重ねると、つい「手伝ってあげたい」「代わりにやってあげたい」と思ってしまいがちです。
でも、やりすぎると“できること”まで減らしてしまうこともあるんですね。
私は、「困っているときだけ手を出す」ように意識を変えたことで、母も「自分でやろう」と前向きになってくれました。
本人が「自分でできること」を書き出してみる
紙に「できること」「少し手伝えばできること」「できないこと」を一緒に整理してみるのがおすすめです。
母と一緒に書き出したとき、「お風呂はまだ大丈夫」「電球替えは無理」と、意外と本人も分かっていることに気づけました。
これだけで“やりすぎ”を防ぐ目安になります。
「見守り=そばにいること」だけじゃない
見守りは、物理的にそばにいることだけではありません。
私は、朝と夕方に「おはよう」「今日も元気よ」とLINEを送り合うようにしています。これだけでもお互い安心できるんです。
電話やメッセージ、声かけアラームなど、方法はいろいろあります。
定期的な「チェック項目」を決めておく
週1回、通院の予定・食事の内容・薬の残量など、チェックしておくべき項目を事前に決めておくと安心です。
私はチェックリストを作って、母と一緒に週末に振り返るようにしています。お互い気負いすぎずに続けられるんです。
見守る側も「無理しない」のが長続きのコツ
見守る側が疲れてしまっては、本末転倒です。
私は、「今日はできなくてもOK」「週1回の見守りでも安心できる仕組みを作ればいい」と考えるようにしています。
気持ちの負担を減らすことで、やさしい見守りが続けられるようになります。
おわりに
見守りの第一歩は、「自分でできる範囲」をお互いに知ること。
全部抱え込まなくてもいい。できることから、できる形で。そんなやさしい見守りを、一緒に作っていきませんか?