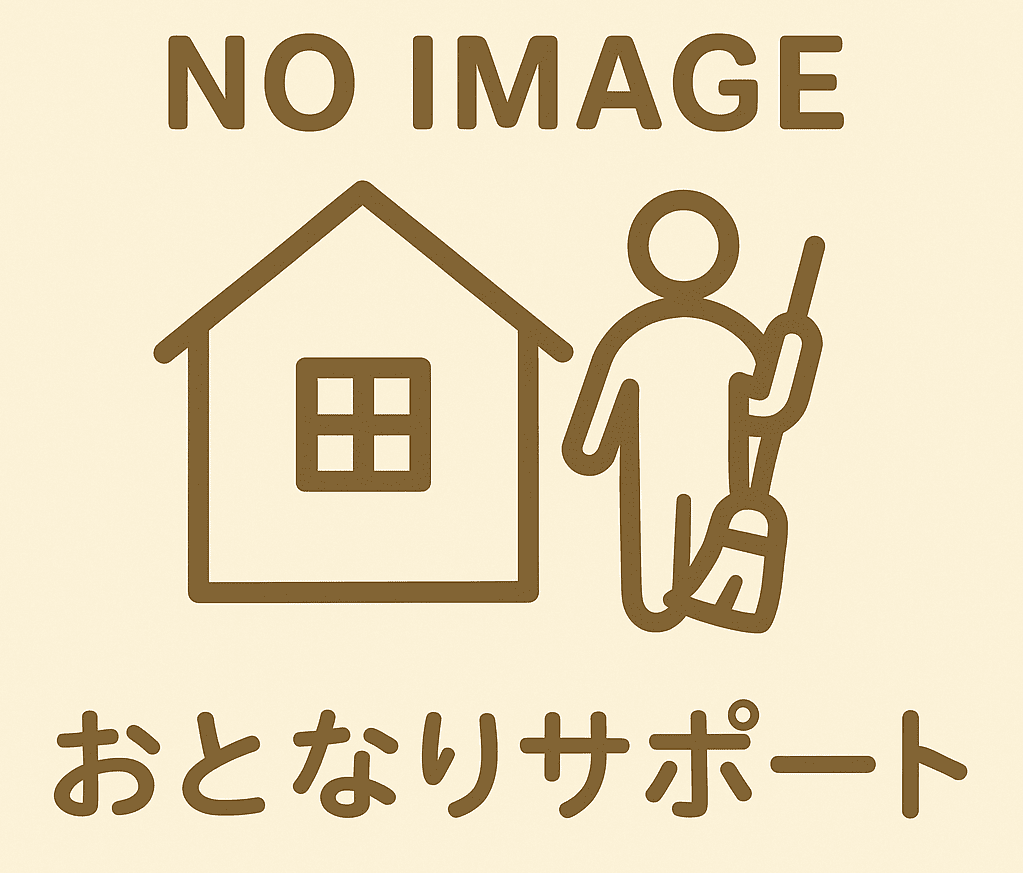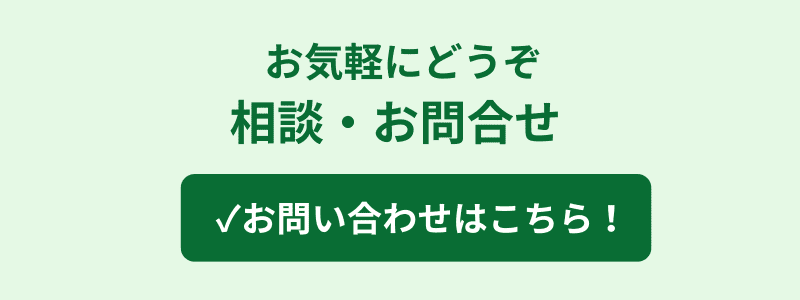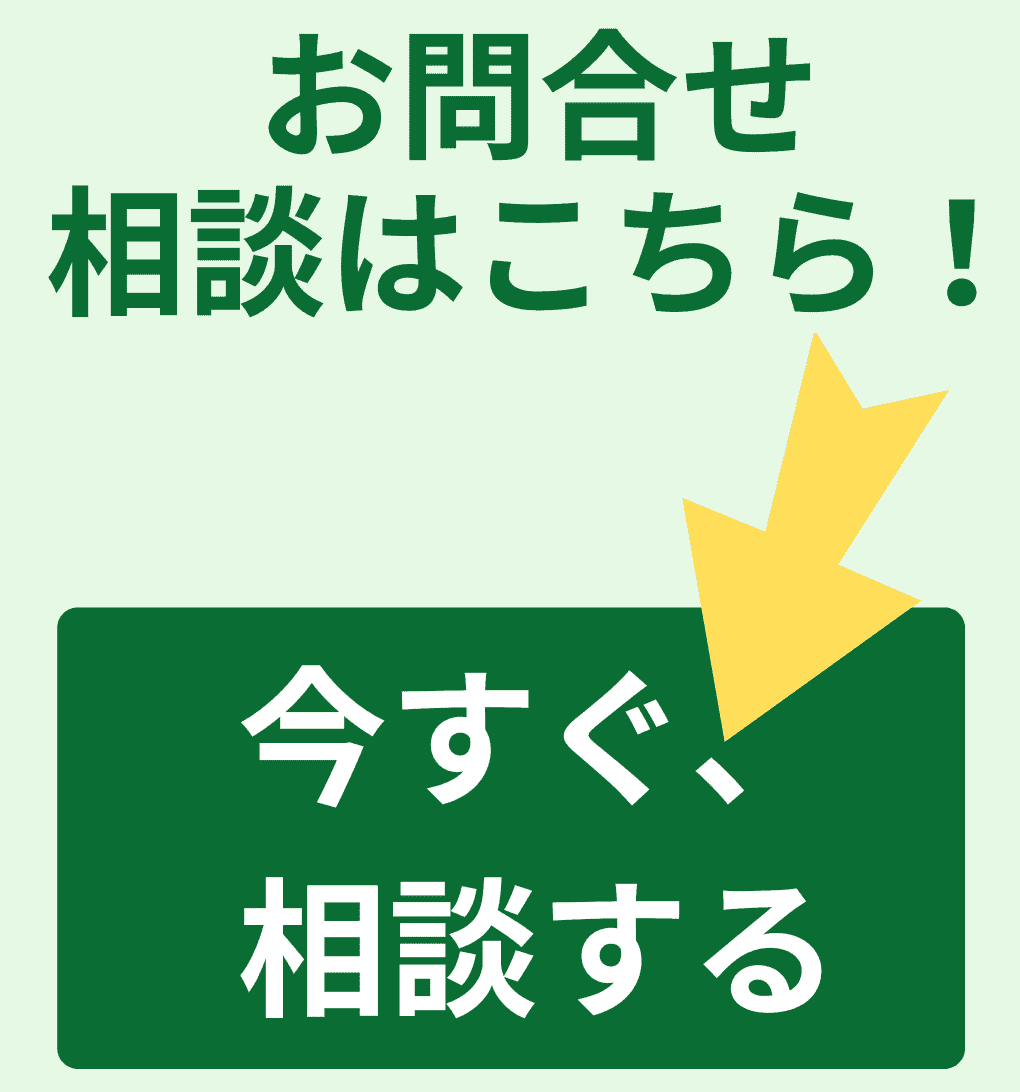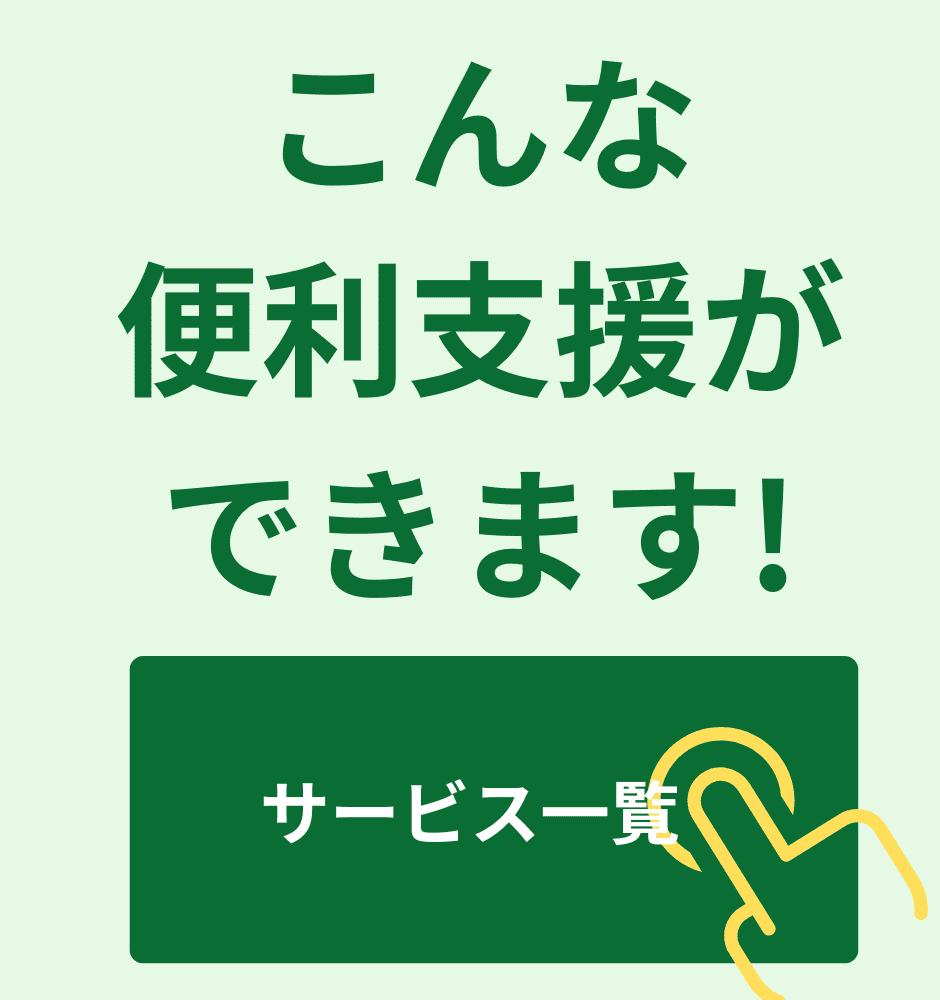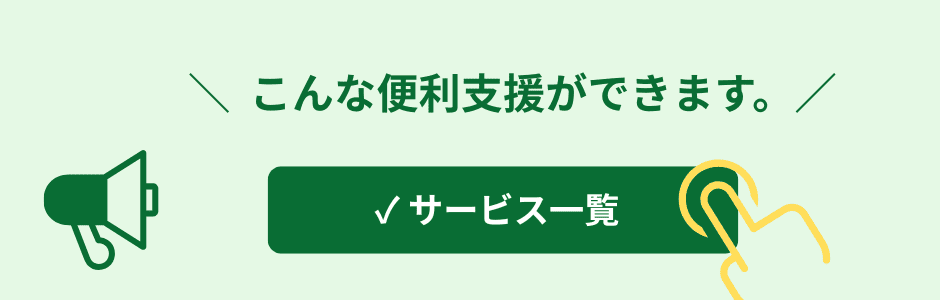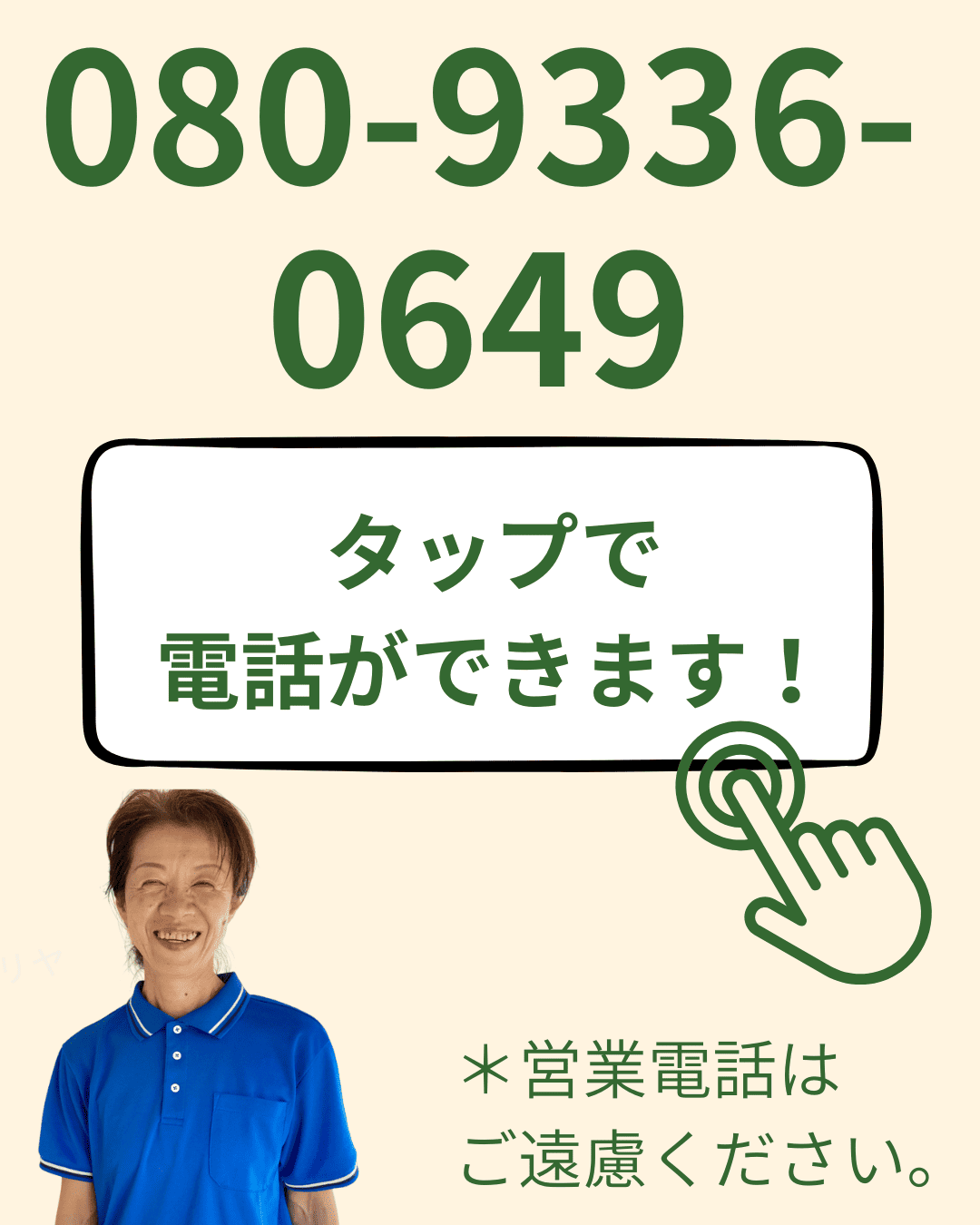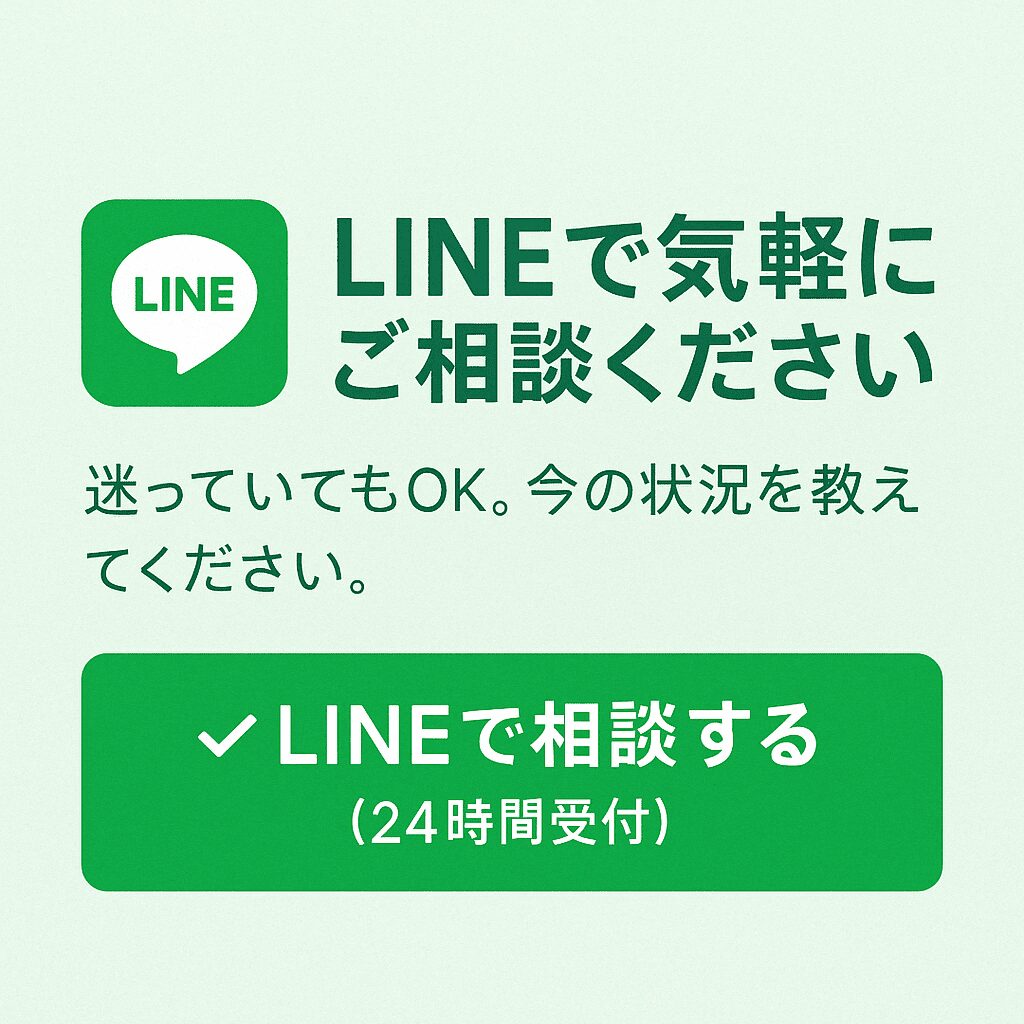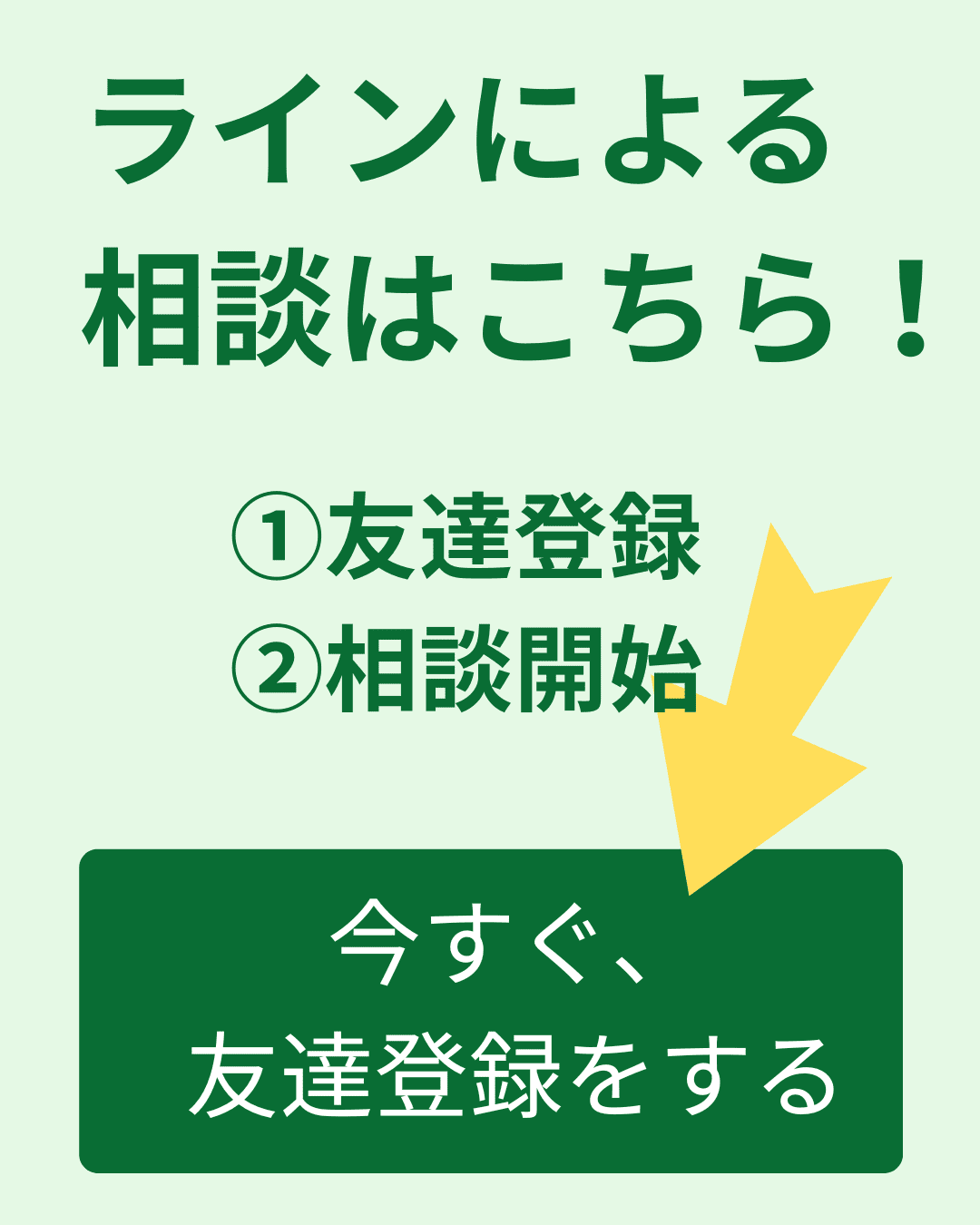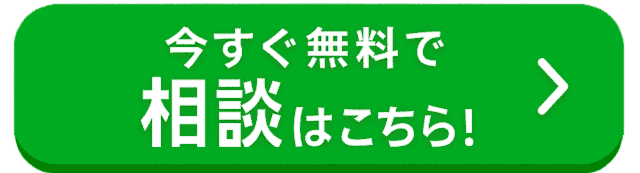不用品を運び出すときに便利な「荷物仕分け袋」
「不用品をまとめたいけれど、どこから手をつけていいか分からない」「まとめたものが重くて持ちづらい」そんなお悩み、ありませんか?
私も昔、実家の片付けをしていたときに、いろんなモノをごちゃ混ぜに袋に入れてしまって、あとから仕分けに手間取った経験があります。それ以来、「仕分け袋」をうまく使うことで作業が格段にラクになったんですよ。
今回は、不用品をスムーズに運び出すための“仕分け袋の活用術”をお伝えしますね。
袋は「種類ごと」に分けて使いましょう
私が実践しているのは、「燃えるごみ用」「リサイクル用」「まだ使えそうな物用」といった感じで、袋を用途別に分けることです。
100円ショップなどで色の違う袋やラベル付きの袋を選ぶと、見た目でも分かりやすくなります。私はそれぞれに名前を書いた紙を貼って、中身を間違えないようにしています。
最近では、ダイソーやセリアなどで売られている「自立型仕分けバッグ(45L対応、ラベル付き)」が特に便利でしたよ。折りたたみ式で、使わないときは収納にも困りません。
小さくても“自立する袋”が便利です
仕分け袋には、床に置いたときにくたっとならない「自立型」の袋を選ぶのがポイントです。
私は布地タイプのトート型や、プラスチックの折りたたみコンテナをよく使います。中身が少なくても倒れないので、両手が空いて作業しやすくなるんです。
重い物は“1袋に詰めすぎない”のがコツ
不用品の中には、食器や本など意外と重たいものもありますよね。私は1袋に詰めすぎず、「少し物足りないかな?」くらいで留めておくようにしています。
両手で持てる重さか、片手でも持ち上げられるかを目安にすると、あとで運びやすくて助かります。
「まとめて運ぶ」にはキャリーもおすすめ
私は仕分けた袋をまとめて運ぶときに、小さなキャリーカートを使っています。庭から車まで、距離があるときにとても便利ですよ。
袋に持ち手が付いていると、引っ掛けて移動できるのでなおさらラクになります。
最後に「捨てる・渡す・残す」で分けておく
仕分け袋を使いながら、不用品は「捨てる物」「誰かに渡す物」「保留して後で考える物」の3つに分けるようにしています。
この方法なら、迷って手が止まってしまうことも減りますし、家族と共有するときにも説明しやすいですよ。
作業の流れを「時間割」にして進めやすく
私は片付ける部屋やエリアごとに「30分で仕分け → 15分休憩」といった時間割を作って取り組むようにしています。タイマーを使うと、集中力も持続しますよ。
仕分け後はどうする?処分・保管・譲渡の方法
それぞれの袋の中身をどう処理するかも大事です。
- 「捨てる物」→ 南島原市のごみ出しルールに従って処分。粗大ごみの場合は市役所に事前連絡を
- 「誰かに渡す物」→ フリマアプリ、寄付団体、近所の知人などに連絡
- 「保留」→ 保管スペースにまとめてラベリング。一定期間見直して判断
高齢の家族や遠方の方との作業には配慮を
高齢の親が一緒に作業する場合は、無理をさせず休憩を多めに取るようにしています。遠方から片付けに来た場合は、スケジュールを事前に家族と共有しておくとスムーズですよ。
南島原市で使える不用品処分の情報
- 粗大ごみ受付:南島原市役所環境水道部 環境課(0957-73-6644)に事前連絡
- リサイクルショップ:市内には家具・雑貨を扱う店舗も複数あり
- 不用品回収業者:便利屋さんと連携しているところも。運搬・分別込みで相談可能
南島原市役所・粗大ごみの収集場所に関すること
おわりに
不用品を運び出すときのストレスは、「袋の使い方」を工夫するだけでずいぶん変わってきます。
体への負担を減らしながら、効率よく、そして自分に合った方法で作業を進めてみてくださいね。
楽しんで進めるために、音楽をかけたり、作業後のご褒美を用意したりするのもおすすめですよ。

お電話による問い合わせはこちら
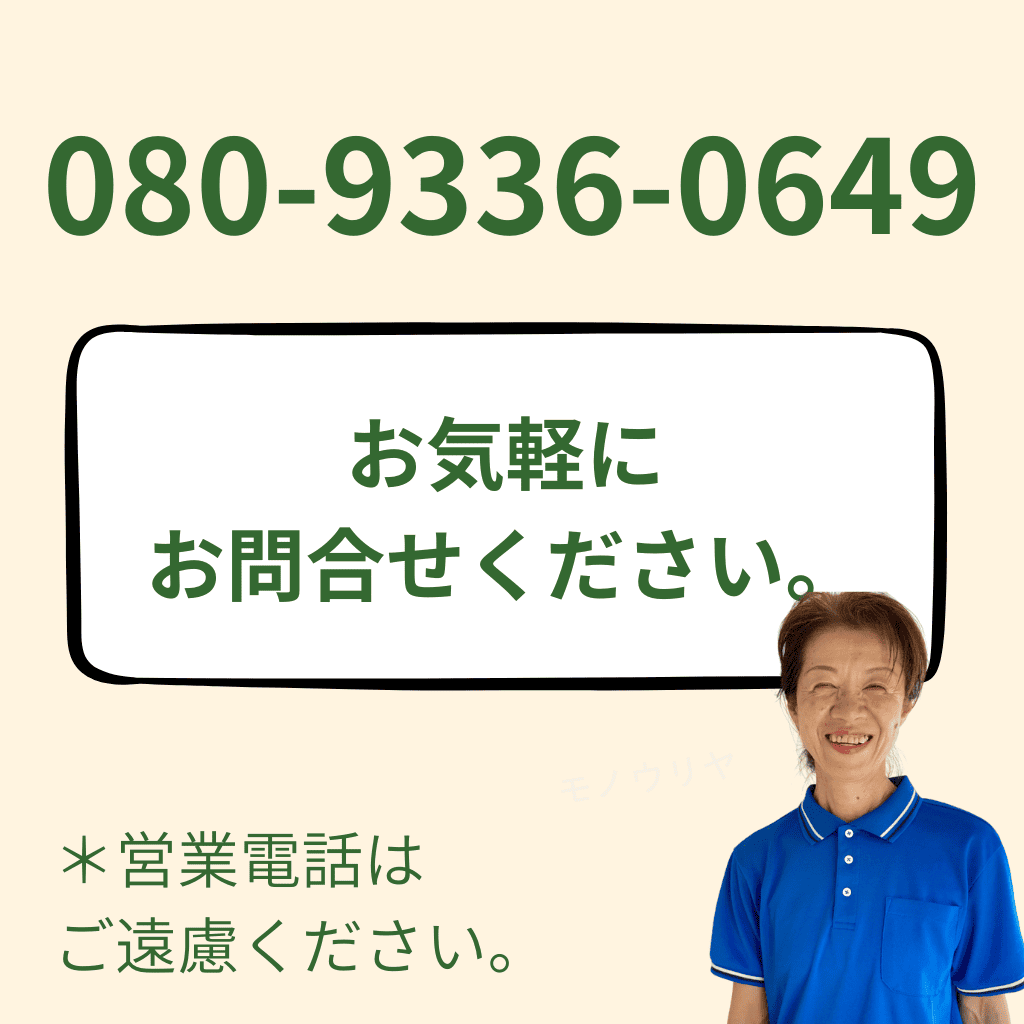
フォームよる問い合わせはこちら
LINEによるご相談はこちら!
- ✅ 写真を送って相談できる
- ✅ 空き時間に返信できる
- ✅ 作業の見積もりが無料でわかる